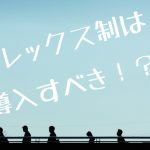経営者にとって、従業員の退職金制度を整備することは大切なことですが、どのように導入したらよいのか迷われる方も少なくありません。そこでご提案したいのが中退共です。 中退共には平成28年現在、約36万以上の中小企業が加入しており、中小企業の退職金制度を支えています。
ここでは、掛金が全額損金扱いになるため税負担が軽減されたり、国から掛金の助成が受けられたりという会社にとってメリットのある中退共について、詳しくご説明していきます。
目次
1.中退共(中小企業退職金共済制度)とは?
中退共とは、正式名を中小企業退職金共済といい、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業部が運営しているものです。 会社が月々の掛金を支払い、そこへ国が掛金の一部を助成する形となっています。
ここでは、中退共へ加入するために必要な条件や月々の掛金、転職した場合はどうなるのか、また中退共加入のメリットやデメリットについてご説明していきます。
1−1.中退共への加入条件とは
中退共に加入できる企業、または加入させる従業員についての条件について確認していきましょう。
【中退共に加入できる企業の条件】
中退共に加入する企業は「共済契約者」となりますが、加入するためには次の(a)常用従業員数か(b)資本金・出資金のいずれかの条件を満たす必要があります。
| 業種 | (a)常用従業員数 | (b)資本金・出資金 |
|---|---|---|
| 一般業種(製造業、建設業等) | 300人以下 | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
ここでいう「常用従業員」とは、一週間の所定労働時間数が正社員とおおむね同等であって、雇用期間の定めがなく、2ヶ月を超える雇用期間がある従業員をさします。
【中退共に加入できる従業員の条件】
原則として、授業員は全員加入させることになりますが(被共済者)、次にあてはまる従業員は必ずしも加入させなくてもよいとされています。
- 期間を定めて雇用される従業員
- 季節的業務で雇用される従業員
- 試用期間中の従業員
- 短時間労働の従業員
- 休職中の従業員
- 定年など相当の期間内に雇用関係が終了する従業員
また、次の要件に該当する従業員は加入することができませんので注意が必要です。
- 中退共制度に加入している者
- 特定業種退職金共済制度に加入している者
- 加入することに反対している従業員
- 小規模共済制度に加入している者
1−2.中退共の掛け金
中退共の掛金は全部で16種類あり、会社は従業員ごとにこれらの中から任意に選択することができます。
| 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
| 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | |
| 22,000円 | 24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
【パートの取り扱い】
正社員よりも1週間の所定労働時間数が短いパート従業員には、上記の掛金だけでなく次に挙げる掛金でも加入が可能です。ただし、短時間労働者であることの証明として「労働条件通知書」や「労働契約書」の写しが必要になります。
| 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
1−3.転職した場合どうなるの?
転職前の会社で中退共に加入していた場合、転職するとこれまで掛けてきたものはどうなってしまうのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。実は、中退共では転職しても掛金を納付してきた実績を通算することができます。
【転職先も中退共の場合】
中退共に加入している会社から他の中退共加入会社に転職をした場合は、次の3つの要件を満たせばこれまでの納付実績を新しい契約に通算することができます。
- 納付月数が12ヶ月以上ある
- 退職してから3年以内に申し出ること
- 退職した会社で退職金を請求していない
なお、会社都合で転職になった場合は、納付月数が12ヶ月に満たなくても通算できますが、厚生労働大臣の認定が必要となります。
【特定業種退職金共済制度と通算する場合】
中退共制度は特定業種退職金共済制度と通算することができますが、次の4つの要件を満たす必要があります。
- 退職してから3年以内である
- 退職した会社で退職金を請求していない
- 当該加入従業員が通算を希望し申出ていること
- 退職の理由が当該従業員に責任がないことを厚生労働大臣が認めている
【特定退職金共済制度と通算する場合】
中退共制度は特定退職金共済制度と通算することもできますが、次の2つの要件を満たす必要があります。
- 退職後3年以内に退職金の請求をせず、もう一方の制度の被共済者となり、通算の申し込みをする
- 中退共と特定退職金共済団体間で退職金引き渡し契約を締結している
このように、これまでの掛金は退職しても転職先の中退共、特定業種退職金共済制度、特定退職金共済制度と通算することができるため、退職するたびに退職金を受け取るのではなく、真の退職時にまとまった退職金を得ることができます。
1−4.事業者側労働者側のメリットデメリット
中退共にはどのようなメリットやデメリットがあるのか、事業者側と労働者側に分けて考えてみましょう。
【事業者側】
(1)メリット
- 掛金全額が損金に算入できるので、会社としての税負担が軽減される
- 退職金の支払い時に会社が不利益を被るリスクを回避できる
- 退職金の管理が簡単になる
- 国から補助金がもらえる
(2)デメリット
- 掛金の減額が難しいので適切な掛金を設定する必要がある
- 掛金の返金は不可である
- 懲戒解雇した従業員にも退職金が支払われてしまう
- 事業主は受け取る権利がない
【労働者側】
(1)メリット
- 24ヶ月勤務すれば掛け金を上回る退職金が積み立てられる
- 掛金に税金が課せられない
- 提携するホテルやレジャー施設を優待価格で利用できる
(2)デメリット
- 勤務期間が24ヶ月未満の場合損してしまうケースがある
- 在職中に死亡した場合の遺族への補償が不十分である
2.退職金額についてモデルケースを使ってわかりやすく説明
中退共の退職金は、大まかにいうと「基本退職金+付加退職金」で計算されます。基本退職金とは、月額掛金と納付月数に応じて固定で定められており、利回りは1%を想定して運用されます。また、付加退職金とは、基本退職金に上乗せするもので、支給率は厚生労働大臣が定めます。
中退共の退職金は、勤続期間によって次のような特徴があります。・勤続期間11ヶ月以下:支給されない
- 勤続期間12ヶ月以上23ヶ月以下:退職金<掛金総額
- 勤続期間24ヶ月以上42ヶ月以下:掛金相当額
- 勤続期間43ヶ月以上:長期勤務になるほど有利になる
ではここからは、具体的なモデルケースで中退共退職金をシミュレーションしてみましょう。
2−1.モデルケース1
<従業員A(24歳)のために月額掛金1万円を20ヶ月納付した場合>
区分掛金納付月数(*)20ヶ月(対応退職金額9,000円)が10本なので
9,000円×10本=90,000円
別表1(http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/sisan/sisan04.html)参照
よって、退職金支給額は90,000円となります。
(*)区分掛金納付月数:掛金月額を千円ごとに区分した場合における各区分ごとの納付月数をいい、各単位を「本」と表記します。
2−2.モデルケース2
<従業員B(55歳)のために月額掛金1万円を25年間納付した場合>
区分掛金納付月数25年間=300ヶ月(対応退職金額342,080円)が10本なので
342,080円×10本=3,420,800円
別表2(http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/sisan/sisan05_03.html)参照
よって、退職金支給額は3,420,800円となります。
3.中退共への加入手続き
中退共への加入手続きは、会社が初めて中退共制度に加入する「新規加入」手続きと、中退共制度に加入している企業で従業員を追加で加入させる場合の「追加加入」手続きとがありますので、それぞれの手続き方法についてご説明していきます。
【会社の「新規加入」手続きについて】
(1)従業員の同意を得る
すでに触れましたが、原則として従業員全員を加入させることとなっています(除外される従業員も定められています)。
(2)月額掛金を決定する
従業員それぞれの月額掛金を決定します。
(3)提出書類を作成する
「退職金共済契約申込書(新規用)」と「預金口座振替依頼書」を作成します。

(参考:独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部)
(4)添付書類を準備する
「中小企業者であることの証明書」や「短時間労働者であることの証明書」などの添付書類が必要かどうか確認し、必要であれば準備します。
(5)書類を提出する
作成した書類は、金融機関(ただし、ゆうちょ銀行、農協、漁業、ネット銀行、外資系銀行は除く)または委託事業主団体の窓口に提出します。
(6)契約成立
退職金共済契約申込書の審査が終了すると、本部から事業主へ各従業員の「退職金共済手帳」が送付されます。
【「追加加入」の手続き】
(1)従業員の同意を得る
追加で加入させる従業員の同意を得ます。
(2)月額掛金を決定する
追加加入させる従業員の月額掛金を決定します。
(3)提出書類を作成する
「退職金共済契約申込書(追加用)」を作成します。
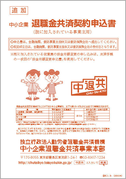
(参考:独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部)
(3)添付書類を準備する
「短時間労働者であることの証明書」などの添付書類が必要な場合がありますので、確認し準備します。
(4)書類を提出する
金融機関(ゆうちょ銀行、農協、漁業、ネット銀行、外資系銀行を除く)または委託事業主団体の窓口に提出します。
(5)契約成立
退職金共済契約申込書の審査が終了すると、中退共本部から事業主へ従業員の「退職金共済手帳」が送付されます。
4.まとめ

従業員のために中退共に加入し退職金制度を導入することは、会社にとって経費が増大することになります。しかし、退職金制度が確立されれば、従業員の労働意欲が向上し生産性がアップすることが見込まれるほか、長期雇用や新しい有能な人材の確保がしやすくなることも期待できます。
まだ退職金制度を導入していないのであれば、中退共の内容やメリット・デメリットをしっかりと理解した上で導入を検討してみてはいかがでしょうか?